○神山町教育委員会処務細則
昭和42年3月7日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 教育委員会の事務処理及び職員の服務に関しては、法令その他別に定めるものを除く外この規則の定めるところによる。
(事務処理)
第2条 教育委員会の事務はすべて迅速、かつ適確に処理し、民主的にして能率的な行政の確保を図らなければならない。
第2章 事務処理
第1節 決裁及び代決
(決裁)
第3条 すべての事務は、上司の決裁を経なければこれを処理してはならない。
2 書類の決裁の証としては、押印するものとする。
(決裁の順序)
第4条 事務の決裁は特別な事由がある場合を除いては、次の順序によって速かに行わなければならない。
(1) 係、係長、教育次長補佐、教育次長、教育長の順
(2) 前号のほか経費を伴う決裁については、町長事務部局関係課及び総務危機管理課長、参事、副町長、町長の順に合議することとする。
(3) 長の委任事務及び補助執行事務については、第1号の規定により教育長の決裁を得たうえ参事、副町長、町長の決裁を受けなければならない。
(教育長事務の代決)
第5条 教育長不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
(教育次長事務の代決)
第6条 教育次長が不在のときは、教育次長補佐が教育次長の事務を代決する。
(教育長、教育次長不在の時の事務代決)
第7条 教育長、教育次長共に不在のときは、在席の教育次長補佐がこれを代決する。
(代決の制限)
第8条 重要又は異例な事務若しくは紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事務については、前3条の規定にかかわらずあらかじめ処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものを除いては、これを代決することができない。
(後閲)
第9条 前4条の規定によって代決した事務については代決者において「要後閲」の印を押し、施行後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決者の責任)
第10条 代決者は、代決した事項についてその責任を負わなければならない。
第2節 専決
(専決の範囲)
第11条 委員会が教育長に委任した事項及び教育長の職務権限に属する事項について教育次長及びその代決者はその属する事務の一部を専決することができる。
(教育次長専決)
第12条 教育次長は、神山町教育委員会の組織及び運営に関する規則(昭和42年教委規則第1号)第30条に規定する事務分掌のうち次の事項に該当する軽易な事務を専決する。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 定例の統計報告その他諸調査及び届書の査閲の処理をすること。
(3) 行政官庁その他の行政機関の軽易な指令通達等を伝達又は交付すること。
(4) 軽易な事項を行政機関へ進達し又は調査報告すること。
(5) 軽易な文書の収受、発送及び証明、照会、回答等に関すること。
(6) 神山町財務規則(平成4年規則第22号)別表第1(第4条関係)第2の規定を準用する。
(7) 前各号のほか、軽易と認められるもの
(専決の制限)
第13条 社会的問題となり、若しくは紛議を生じ又は生ずるおそれがあると認められる事務については、前条の規定にかかわらずあらかじめ処理について指示を受けたもののほか、これを専決することができない。
(専決者の責任)
第14条 専決者は、専決した事項についてその責任を負わなければならない。
第3章 文書
第1節 文書等の収受及び配付
(文書取扱の原則)
第15条 文書はすべて正確かつ迅速に処理し常に整備して一般事務能率の向上に資するよう努めなければならない。
(文書の収受)
第16条 執務時間中に教育委員会に到達した文書、図書、金券、物品等は、教育次長が収受する。
2 庶務係に文書取扱者を置く。
3 文書取扱者は、上司の命を受け文書の収受、発送及び整理、保管に関する事務を掌理する。
(文書の配付)
第17条 収受した文書は、次の各号によって直ちに配付しなければならない。
(1) 親展でない文書は、庶務係長が開封し文書整理簿(電報は電報処理簿)に登載し、その文書に受付印を押して受付番号及び収受年月日を記入し文書整理簿(電報は電報処理簿)によって教育次長に交付しなければならない。
(2) 親展文書は、開封せず、親展文書処理簿(親展電報は電報処理簿に登載し摘要欄に親展の旨記入する。)に登載して名あて人に交付しなければならない。
(3) 秘密を要する文書は、秘書整理簿に登載して教育長又は特に指名されたものに交付しなければならない。
(4) 現金、金券、有価証券又は図書物品の添付のある文書は、文書の欄外及び文書整理簿の摘要欄にその旨を記載して、文書は通常の方法で配付し現金、金券及び有価証券は金券等受渡簿に、図書物品は図書物品受渡簿に登載して会計管理者又は教育次長に交付しなければならない。
(5) 文書の添付のない現金、金券、有価証券又は図書物品の送付を受けたときは、金券等受渡簿又は物品受渡簿の欄外にその旨記入の上、前号後段の方法によって交付しなければならない。交付先の不明なときは、その判明するまで庶務係長が保管するものとする。
(6) 収入印紙又は郵便切手を貼付若しくは添付した文書は、文書整理簿の摘要欄にその貼付額を記載して教育次長に交付しなければならない。
(7) 別紙物品、収入印紙等を添付又は貼付する旨の記載があってそれがないときは、文書整理簿の摘要欄にその旨を記載して配付しなければならない。
(8) 官報、新聞、その他軽易な文書は、文書整理簿に登載しないで受付印を押し、教育長又は教育次長に配付しなければならない。
2 前項の文書で訴願書、審査請求書及び期限の定めのある文書等収受の日時が権利義務に関係があるものについては、収受の時刻を欄外に記入しその封筒を添付しなければならない。
(文書整理簿の返付)
第18条 教育次長及び名あて人は、前条の金品又は文書の配付を受けたときは、整理簿又は処理簿に押印して庶務係長に返付しなければならない。
(配付前の閲覧)
第19条 収受文書で重要若しくは異例と認められるものは配付前に教育長の閲覧をへなければならない。
(口頭又は電話による受付)
第20条 口頭又は電話により受け付けた事項で重要なものは、口頭受付簿又は電話受付簿にその要領を記載して教育次長に報告しなければならない。
(各係に関係のある事務の主管)
第21条 各係に関係のある事項は、その関係が最も深い係が主管するものとする。その主管について意見が異るときは、教育次長が定める。
(主管でない文書の返付)
第22条 配付を受けた文書がその主管でないと認められるものがあるときは、速かに庶務係長に返付しなければならない。
(直接受理文書)
第23条 庶務係長を経ずして直接受理した公文書は遅滞なく庶務係長に回付し、収受の手続を経なければならない。
第2節 文書の処理及び起案
(配付を受けた文書の処理)
第24条 文書の配付を受けたときは、教育次長は自ら処理するもののほか、係長若しくは係員に配付して速かに処理させなければならない。
2 重要若しくは異例に属する事件は、予め上司の指揮を受けて処理しなければならない。
3 配付を受けた文書は、直ちに処理し、遅くとも3日を過ぎてはならない。合議を受けたときも同様とする。
(至急文書の処理)
第25条 至急に処理しなければならない文書は、欄外上部に「至急処理」印を押印して回議するものとし、即時処理しなければならない場合は、事務主任者が持ち回るものとする。
(秘密文書の処理)
第26条 秘密文書の処理は、教育次長又は特に指名された者が、立案し、欄外上部に「秘」の文字を朱書して自ら持ち回り、又は秘書袋に封入して授受しなければならない。
(文書の発信名義)
第27条 公文書は、すべて教育委員会名又は教育長名をもってしなければならない。ただし、軽易なものにあっては、教育次長名又は教育委員会事務局名もってすることができる。
(文書の公明)
第28条 文書、簿冊等は教育長の承認を経なければ他人に示し若しくは謄写を与へ又は事務局外に持ち出すことができない。
(文書の起案)
第29条 教育次長は所管事務について異例又は重要若しくは機密に属する事務であって、自ら企画立案し、自ら処理するものを除いては、事務主任者に企画立案させることを例とする。
(起案用紙)
第30条 立案は起案用紙を用いなければならない。ただし、軽易な事件については本書の余白にその処理を朱書してこれに代えることができる。
2 成規の例式あるものについては、帳簿を作成し、これを立案用紙に代えることができる。
(起案上の留意点)
第31条 立案については次のことに留意しなければならない。
(1) 簡単かつ平易な言葉を用いる。
(2) 重要部分の字句を訂正したときは、その個所に訂正者が捺印する
(3) 特に重要又は異例な事件に関するもので立案の趣旨を説明する必要があると認められるときは、処理案の前文にその趣旨を簡明に記述すること。
(4) 同一案件で更に起案を必要とするものは、その完結に至るまで関係決裁文書又は供覧文書を添付すること。
(5) 関係案件は、支障のない限り一起案とすること。
(6) 委員会の議決又は委員会に報告を必要とするものは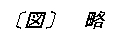 又は
又は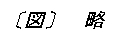 と標記件名の上部に朱記すること。
と標記件名の上部に朱記すること。
(起案者の特別扱)
第32条 起案書には、必要に応じ「重要」「秘」「親展」「至急」「速達」「書留」「配達証明」「経由」「掲示」等欄外にその取扱いを朱書又は押印するものとする。
(回議)
第33条 立案が完了したときは、職氏名を記入し捺印のうちその事務内容に応じ関係係員及び上司に提出し決裁を受けなければならない。
(回議の順序)
第34条 第4条の規定は、回議についてこれを準用する。
(回議文書の査閲)
第35条 回議文書を受けたときは、直ちに内容を確認あるいは検討し捺印の上次に回議しなければならない。調査上日時を要するときは、立案者にその旨を通知しなければならない。
2 回議文書に異議あるときは、その立案者と協議し、なお意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。
3 回議文書を廃案し又は内容を変更したときは、その旨回議者に通知しなければならない。
(重要な文書の回議)
第36条 委員会の議決又は、委員会に報告を必要とする文書、対外文書で重要なもの並びに公表する文書は庶務係に回議しなければならない。
第37条 委員会の議決、又は報告を必要とする文書は、教育長の決裁又は閲覧後庶務係に回付しなければならない。ただし、委員会の議決を必要とする文書は議案として作成しなければならない。
2 庶務係において前項の文書の回付を受けたときは、委員会の議決又は、報告の手続を行い議決又は報告後はその旨及び年月日を記入して所管係に返付する。
第38条 町議会の議決を必要とする文書は委員会の議決後、庶務係を経て町長に送付しなければならない。
(1) 進退、給与、その他身分取扱いに関すること。
(2) 機密に属し又は特に説明の要があるもの
第3節 文書の浄書及び発送等
(浄書及び発送の手続)
第40条 発送文書又は公布若しくは公示する文書は、原則として庶務係で作成するものとし、起案書に番号及び年月日を記入し、浄書、立案者で校合し、公印を押し起案書に施行年月日を記入、起案書に契印の上庶務係の文書取扱者に回付するものとする。
2 印刷した文書であって事の軽易なものは、公印及び契印を省略することができる。
3 庶務係の文書取扱者は回付を受けた文書について文書整理簿に朱書をもって登載するものとする。
4 発送又は公布若しくは公示の手続をおえたときは、その起案書を庶務係に返付しなければならない。
(文書の番号)
第41条 文書(指令を含む。)の番号は、毎年1月1日から起し、収受及び発送を通じて、一連番号を用い、同一事件の往復には、完結に至るまで翌年にわたる場合といえども同一(枝番)の番号を用いなければならない。
(直接交付文書等の処理)
第42条 来庁者又は附近官公署若しくは住民等に直接交付する文書、物品等は、文書等送致簿に登載し、受領の署名を徴さなければならない。ただし、軽易なものはこの限りでない。
(電話による事務処理)
第43条 電話によって処理しようとする事項のうち重要なものは、電話伺簿に記載し、教育次長の承認を経て、通知しなければならない。
(教育委員会日誌)
第44条 教育次長は毎日必要な事項を教育委員会日誌に記録しなければならない。
第4節 帳簿用紙等
(帳簿、用紙の様式)
第45条 教育委員会事務局の事務は、別に定めるもののほかは、神山町文書取扱規程(平成15年訓令第3号)の例による帳簿及び用紙によって処理するものとする。
第5節 公文例式
(公文令達の様式)
第46条 公文令達及びその他の文例の様式は神山町文書取扱規程の例による。
(通常公文書の例式)
第47条 公文書は別に例式があるものを除いては、番号、発送年月日、発送先を記し、その種類によっては、委員会名、公職名又は事務局名を記し、相当の公印を押し、契印をしなければならない。ただし、管内に発送する軽易な文書は特に押印を要するものを除いては、公印及び契印を押すことを省略することができる。
第6節 文書の編集及び保存
第48条 文書の編集及び保存は神山町文書取扱規程を準用する。ただし、条文中「総務課長」、「町長」とあるのは「教育次長」及び「教育長」と読みかえるものとする。
第4章 服務心得
第49条 事務局職員の服務については、神山町職員服務規程(平成15年訓令第2号)を準用する。
附則
この規則は、昭和42年3月15日から施行する。
附則(昭和50年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規程第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年3月17日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。